- HOME
- 東急コミュニティーについて
- メッセージ

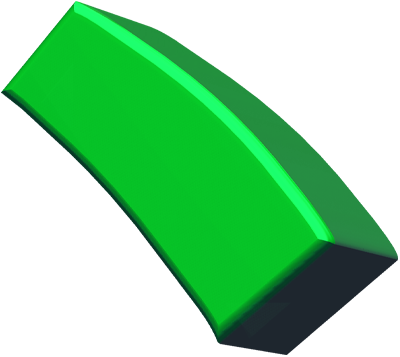
「と、」 を見たら私たちを思い出してください。
1970年。この会社は生まれました。およそ50年前のその時、
すでに社名に「コミュニティー」 という言葉を冠していた。なぜか。
なぜ、「管理」 や「マネジメント」 ではなく「コミュニティー」 と名乗ることを決めたのでしょう。
確かな技術力に基づき、建物・設備の管理をする。当初、この会社の業務の主軸はそこにありました。
しかし、それだけにとどまっていてはいけない。人々の暮らし、生活を支えていく
「コミュニティーを創造していく」 会社であれ。そう強く意識していたからです。
あの日から今日まで、私たちは常に新しい領域へ進出、チャレンジを続け、実績を重ねてきました。
建物を健康に保ち、人々が快適に過ごせるよう支える。
マンションやビルだけでなく、競技場、ホール、空港、学校、公園・・・
あらゆる場「と、」 あつまる人のカンケイを創造していく。私たちの仕事は、公共性が高い仕事です。
今日、私たちは社会に必要とされる「コミュニティー」 を創る会社となりました。
しかし、まだまだ、私たちを必要とする場がたくさんある。
次はどんな場「と、」 どんな人のカンケイを創造していこう?
考えていく、動いていく、私たちでありたい。そう強く、強く、思うのです。
「と、」 =コミュニティーを創る会社








「と、」 を見たら
私たちを思い出してください。
1970年。この会社は生まれました。
およそ50年前のその時、
すでに社名に「コミュニティー」
という言葉を冠していた。なぜか。
なぜ、「管理」 や「マネジメント」 ではなく
「コミュニティー」 と名乗ることを
決めたのでしょう。
確かな技術力に基づき、
建物・設備の管理をする。
当初、この会社の業務の主軸は
そこにありました。しかし、
それだけにとどまっていてはいけない。
人々の暮らし、生活を支えていく
「コミュニティーを創造していく」
会社であれ。そう強く意識していたからです。
あの日から今日まで、私たちは常に
新しい領域へ進出、チャレンジを続け、
実績を重ねてきました。建物を健康に保ち、
人々が快適に過ごせるよう支える。
マンションやビルだけでなく、
競技場、ホール、空港、学校、公園・・・
あらゆる場「と、」 あつまる人の
カンケイを創造していく。
私たちの仕事は、公共性が高い仕事です。
今日、私たちは社会に必要とされる
「コミュニティー」 を創る会社となりました。
しかし、まだまだ、私たちを必要とする
場がたくさんある。次はどんな場「と、」
どんな人のカンケイを創造していこう?
考えていく、動いていく、私たちでありたい。
そう強く、強く、思うのです。
「と、」 =コミュニティーを創る会社
































































ビル屋上看板

技術研修センターNOTIA 入口・立体オブジェ

コンセプトムービー



